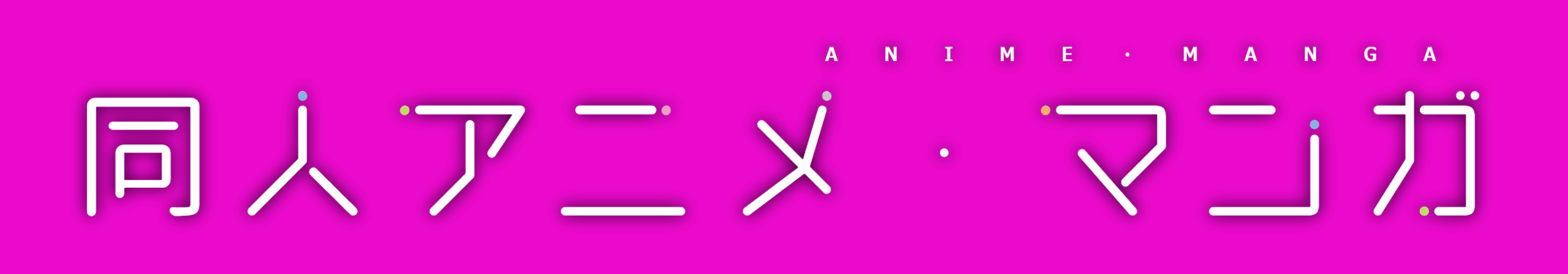同人といいますと、少しものものしい感じをうける方もあるかもしれませんが、何かについてのアマチュアの集まりととっていただきたいと思います。今日単に「同人」といいますと、多くは「小説」「イラスト」「漫画」「音楽」「ゲーム」等々の活動を指すことが多いわけです。これは領域、側面、分野ごとに多数あります。歴史をたどってみても、俳諧、小説等、「同人」として登場し、プロとアマチュアに分かれていったものが多くあります。
歴史によってみても、当時は同人として理解されていたものが、後世には文化の中心として理解されるようになったものもあり、また、レベルの高さや、同人誌専門店等があることにより、素人性や非商業的性質で区別することは困難かとおもわれます。
むしろ、私は同人を以下のような意味で、アマチュア的行為として理解したいと思います。アマチュア(amateur)は、今日では、「素人・非プロ」と理解されていますが、原意は「そのことが好きだからする人」であったわけです。同人は、ある領域でアマチュアとして活動しようとする基本的な気分ともいうべきことではないかともいます。たとえば、商業・経済に搦めとられていない、自由度のある創作活動などは、その現れかもしれません。そして、固定的な(かくかくしかじかの)ものとしてみるのではなく、人の振る舞い、すなわち事的・動的な存在としてみるべきではないかとおもいます。ここでは、私の関わりはじめた今日の同人活動の基本的な性格をお伝えすることをここのねらいとします。厳密な論証ではなく、何らかのかたちで納得していただけるように提示できればと思います。
1,同人メディア
メディアとは、伝達媒介のことです。単に、ひとりで「もそもそ」するのも、同人の在り方かとは思いますが、ここでは表現する・伝達するということを前提にし、その在り方をみていきましょう。
・紙
一見言わずもがなのメディアですが、描いたもの貯めておいたり、人に見せるもっとも基本的な手段であり、また、イベント会場でのスケブ(スケッチブック)のように、作家と読者のふれあいの手段としても用いられます。
・電子データ・WEB
今日では、パソコン等電子機器の発達により、描く(書く)という行為自体を機械を使って行うことが増えています。それゆえ、紙とインク等のみで行っているときよりも、表現及び伝達の可能性がぐっと広がっています。
イラストではAdobe社のPhotoshopに代表されるグラフィックツールや、高繊細プリンター、スキャナー、ペン型の入力機器であるタブレット、高機能マウス等々が比較的身近なものとなってきました。MOやCD-R等の記録媒体が発達し、電子入稿・配布も身近になってきています。
また、WEBの発達により、不特定多数の人に対し、コンテンツを公開することが容易になりました。まさに、パーソナルメディアの時代といえましょう。
・イベント
とはいえ、やはり今日の同人活動の花形はイベント参加といえます。多くはボランティアで運営され、作家は、事前(一部イベントでは当日も可)に申し込み、スペース(会議机一個から半分の幅が多い)を得て、制作物を有償または無償で配布します。そこに、他の作家や、一般参加者が訪れます。一般参加者というのは、当日販売物やスペースのない普通の入場者をいいます。それでも「参加者」と呼んでいるのは、「イベントは全ての参加者によって作られる」という発想によっているからです。
その最大級のものが夏・冬に東京ビッグサイトで行われるコミックマーケット(コミケ・コミケット)です。
コミックマーケット61(2001年冬コミ)のアフターレポート(『コミックマーケット62カタログ』収録)によりますと、2日間での参加サークル22000、入場者は各日18万人(!)にのぼっています。当然設営・撤収、開場前の待機者整理、会場内の交通整理、人気サークルの購入待ち列の整理、委託頒布、安全確保等々想像を絶するような協働のもとに成り立っています。